ASEAN主要7カ国+インド マーケットの入口
現地からの所感|Fi Asia & Vitafoods Bangkok 2025
Fi Asia & Vitafoods(2025年09/17〜19、バンコク・QSNCC国際会議場)は、主催の事前案内ベースで出展750社超・来場23,000人超・来訪70カ国超の規模で、今年は体験型の展示が増え、歩いて回っても楽しい構成でした。
日系では、麺・ベーカリー・ビール向けのアルギン酸提案がとくに目立ちました。タイは日本食のすそ野がどんどん広がる一方で、運営はタイ資本の店も多く、味や食感が「惜しい…!」に落ち着く場面もまだある。そこで“ふわっと膨らむパン”“茹で伸びしにくい麺”“きめ細かい泡のビール”を実現する素材の出番。小さな処方でも口当たりはガラッと変わるので、日本食の底上げ×日系素材の出番はまだまだあるな、という実感です。
会場スナップを3つ。
-
香料ブースでは、寿司レーンみたいな回転テーブルに「チョコ、抹茶、ゆず…」と香り付き試食品が次々流れてくる仕掛け。立ち止まった瞬間に“香りで理解”させ、そのまま商談させるのがうまい。
-
中国勢のブースでは、同時に何人もライバーがスマホで「生配信」。視聴コメントを拾いながら、その場でサンプルや価格の説明まで進むスピード感が圧巻。
-
いっぽう日本の多くのブースは、来てくれた人に機能や事例を丁寧に説明→商談という“対面の深さ”が強み。中国ブースのライブ発信の波とは真逆だけど、信頼を積む感じはやっぱり日系らしい。

食の質を上げる日系素材に勝機
タイの日本食マーケットは年々拡大しているが、現地タイ資本が多く、味や食感に課題が多い。つまり日本品質にはまだまだ及ばないため、そこへアルギン酸や麹など“日本の技術・素材”が入る余地は大きいと実感。 麺のコシ、パンのふわっと感、ビールの泡持ち——小さな処方で体験価値が一段上がり、結果として訪日経験で口の肥えたタイ人にはまり、日本食カテゴリー全体の単価と満足度を押し上げられるはず。
加えて、会場で目立った「同時ライブ配信で一気に商談母集団を作る中国勢」や「回転レーンで“香り・味”を次々試させる香料ブース」の見せ方は、日系も取り入れられる余地あり。“機能性と緻密さ+ライブや演出”で、来年はもっと良い商談チャンスを獲りにいけると思います。
FAQ(Fi Asia & Vitafoods Bangkok 2025)
Q. いつどこで開催されましたか?
A. 2025年9月17日〜19日、バンコク都心のQSNCCで開催されました。
Q. 規模はどのくらいでしたか?
A. 主催の事前案内ベースで出展750社超、来場23,000人超、来訪70カ国超の見込み規模でした(最終確定値は未公表)。
Q. 日系は何が目立ちましたか?
A. アルギン酸(麺・ベーカリー・ビール向け)や麹など、食感・風味を底上げする素材提案が目立ちました。
Q. 具体的な日本企業の例は?
A. 三菱商事ライフサイエンス、KIMICA、イワキ、野村貿易、高砂香料など。
Q. それらの素材が注目される理由は?
A. タイで日本食が年々拡大し、品質の均一化・高付加価値化への需要が高まっているため。少量配合でも“麺のコシ”“パンのふわっと感”“ビールの泡持ち”など体験価値を上げやすいからです。
Q. イベント時の会場レイアウトの特徴は?
A. Fi AsiaはG階、VitafoodsはLG階で、目的別に回遊しやすい分割配置でした。
Q. 他国のブースで印象に残った点は?
A. 中国勢は同時多人数のライブ配信で商談母集団を広げ、香料ブースでは回転寿司レーンのような回転テーブル展示で“香り体験”を連発していた点です。
Q. 日本勢の強みと課題は?
A. 強みは機能性と、対面での丁寧な商談と技術の緻密さ。課題は“スピードと演出”の強化(ライブ配信・即サンプル出荷・即時見積など)です。
Q. タイの日本食市場は拡大している?
A. はい。日本食レストランは2024年に5,916店(前年比+2.9%、+165店)で、2007年745店から約7.9倍と裾野が拡大しています。
Q. 地域別の店舗分布は?
A. バンコク都2,672(+2.7%)、近郊5県873(+2.7%)、その他地方2,371(+3.1%)です。
Q. 業態別の動きは?
A. ラーメン802(+8.2%)、居酒屋480(+9.8%)、蕎麦・うどん36(+16.1%)が増加、一方で寿司は1,279(−6.8%)でした。タイ資本が目立ちます。
Q. タイ外食市場の足元は?
A. 2024年は約5,450億THB(+8.9%)規模、2025年は約5,720億THB見通し(+4.8%)と堅調です。
Q. 来場者の主な属性は?
A. 食品・飲料・サプリ関連の開発、購買、事業責任者が中心で、試食・試飲や機能性相談の需要が高い層です。商談は英語で問題ありません。
Q. 次のバンコクでの食品関連の展示会はいつ?
A. 以下になります。
・2025-10-01〜10-03|BITEC(Bang Na, Bangkok)|Thailand Bakery & Ice-Cream 2025|ベーカリー/アイスクリームの原材料・製菓機器・包装の展示会
・2025-10-02〜10-05|BITEC(Bang Na, Bangkok)|ASEAN Café Show 2025|コーヒー/ティー/ベーカリー/アイス/カカオの総合カフェ産業展
・2025-10-15〜10-17|BITEC(Bang Na, Bangkok)|LogiMAT & LogiFOOD Southeast Asia 2025|食品・コールドチェーンを含む物流/サプライチェーンの展示会
・2026-05-26〜05-30|IMPACT Muang Thong Thani|THAIFEX – Anuga Asia 2026|アジア最大級の食品・飲料総合見本市(参考:タイ最大の食品商談会。来年分も既に予約が始まっており、2025年12月を待たずに予約がいっぱいになりそうな勢いです)
最新の現地事情など、ご不明な点はお気軽にご相談ください。
アジアクリック 高橋学
(以下現地写真が続きます)










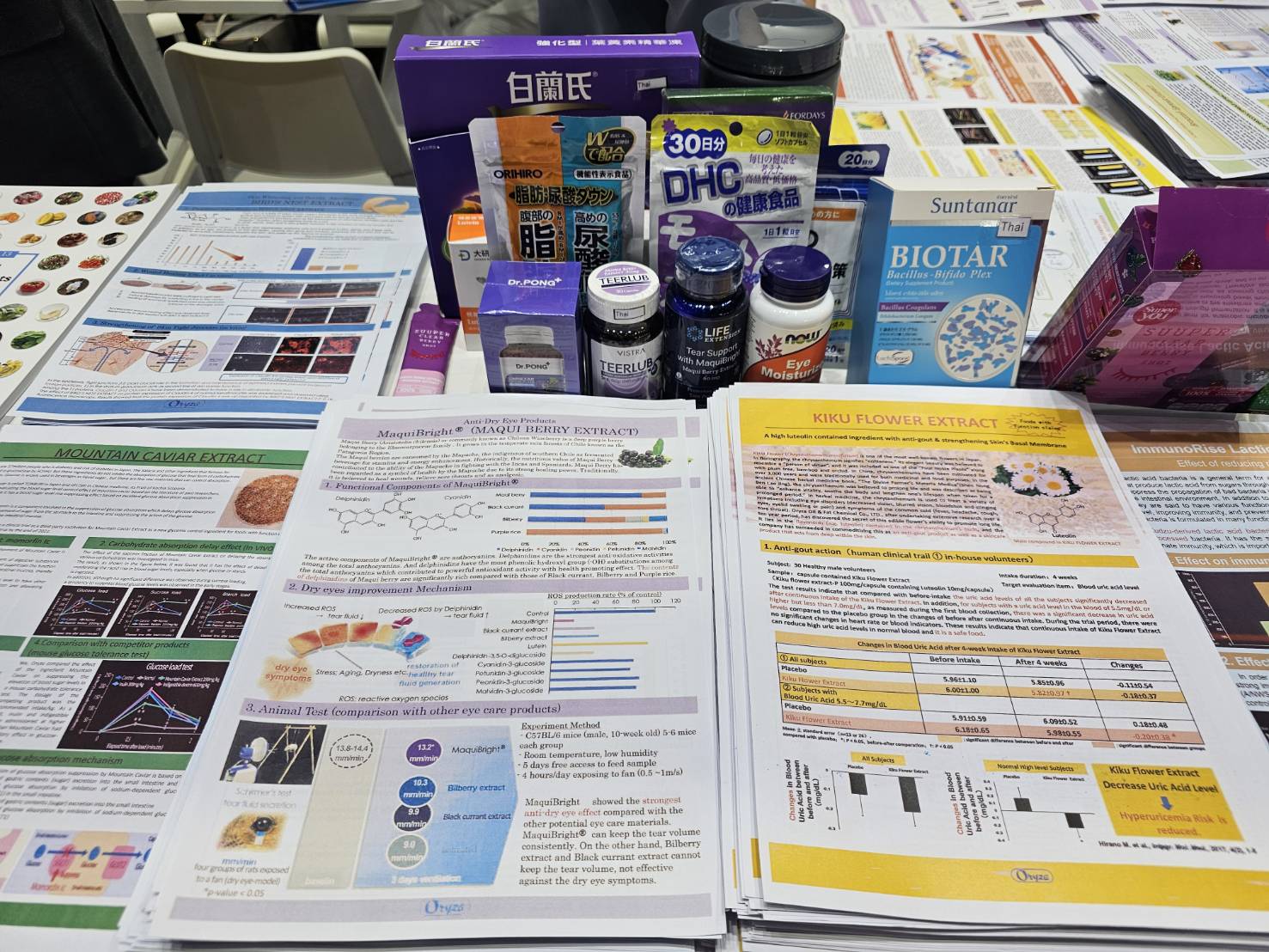
 写真は以上です。
写真は以上です。

結論・概要
バンコク日本博(NIPPON HAKU BANGKOK)は、クイーンシリキット国際会議場で毎年9月初旬ごろに行われるタイ最大級の日本文化フェスです。今年で10年目。教育・旅行・食・サブカルまで日本の体験が集まり、3日間の会期中は10万人以上が訪れます。
初日の会場2階では訪日トラベル商談会(BtoB)を実施。日本側は山形から熊本までの自治体・DMOが13団体、タイ側は旅行会社38社、全6セッション×15分の自由商談形式で進みました(司会進行はアジアクリック・高橋学が務めさせていただきました)。 その結果、家族や6〜12人の少人数で楽しむ高付加価値のFITと、30〜200名のインセンティブの両輪で具体案件が一気に前進。特に長崎・五島列島や群馬の温泉地といった新しい行き先の検討が進み、山形・和歌山など定番の深掘りも着実に動きました。人手不足に伴う宿泊価格上昇や、中国各地の低価格ツアーとの競合が激しくなる中、対面で日本旅行らしい高品質な体験を伝えることで“選ばれる理由”を明確化できると感じました。

商談会の様子
商談の進み方:開始直後から各テーブルで商談が一斉に開始。名刺交換のあと、場所の確認・魅力・最新情報・移動時間・概算費用・受入上限・食や禁忌といった実務ポイントを、日タイ双方がパンフレットとQRコード先の詳細資料を行き来しながらテンポよく商談を進めていく流れでした。
- 日本側の声:6セッションでも途切れず商談できた/新たな有力旅行会社と出会えた/FITとインセンティブで具体送客の話が複数出た/一度で多くの有力会社に会えるので効率的だった
- タイ側の声:長崎・五島列島や群馬の温泉など、既存顧客に提案しやすい新ルートを具体化できた/山形・和歌山など定番も最新の詳細情報で商品化の解像度が上がった/デスクリサーチには限界があるため、継続的な対面やファムトリップの機会がほしい
トピック:途中、くまモンがサプライズ登場し、雰囲気が一段と和みました。熊本への関心喚起にもつながりました。

タイ訪日の課題と打ち手
日本国内では人手不足などを背景に宿泊価格が上昇し、繁忙期はホテル・旅館・バスの確保が難しい状況が続いています。加えて、中国東北部ハルビンから四川省・成都まで中国大陸各地の季節ツアーが格安で販売され、訪日の強力な競合となっています。こうした状況下のもと、日本の地方で好感されたのは
(1)新規性×体験性が高く旅行会社に依頼すべき行き先(長崎・五島列島、群馬の温泉地等)の提案と、
(2)定番(山形・和歌山等)の深掘り=滞在時間と消費価値を魅力的に伸ばす情報提供です。
さらに、「FITモデルコース」と「インセンティブツアーモデルコース」の2種類を事前に用意し、「なぜその地域なのか」「いくらで・いつ・どの規模で受け入れられるのか」を一目でわかる形にするとツアー企画に落とし込みやすく、タイ旅行会社の意思決定も早く前進するでしょう。

高付加価値な「FITグループ」と「インセンティブツアー」を狙おう
タイ市場で日本の地方が選ばれる鍵は、価格ではなく、家族や仲間とともに過ごす「記憶に残る訪日体験」にあります。
高付加価値なFITとインセンティブという二本柱を意識し、モデルシートでその理由と条件を「高付加価値」として見える化することで、次シーズンの実際の送客につながります。
来年以降もこの対面商談の場を継続し、地域の魅力を丁寧にお伝えしていきたいと考えています。
タイをはじめシンガポールやフィリピン等、東南アジアからの訪日誘客に関するご相談は、お気軽にお声がけください。
アジアクリック 高橋学
2025年8月7日〜10日、バンコク・IMPACT Exhibition Center Hall 7-8で「タイ中小企業博覧会 2025(SMART SME EXPO 2025)」が開催。約10,000㎡に、飲食をはじめとした200超のフランチャイズが集結し、4日間で15,463人もの来場者が訪れました。
来場者からは『必要な情報が揃う』『優れたパートナーが見つかる』との声が寄せられるとともに「ビジネスの仕組みや素材についてさらに詳しく知りたい」という前向きな要望も多く、会場全体に高い熱意が感じられました。

商談総額約9億円
主催者発表では、353件の商談成立/商談総額202百万バーツ(約9.1億円:1バーツ=4.5円換算)もの成果とのこと。売上総額287百万バーツ(約12.9億円)、融資申請186百万バーツ(約8.4億円)、総経済効果474百万バーツ(約21.3億円)の見込みと、タイの景気停滞感の中でも新規投資の動きは堅調です。
人気ブランド例
今回とくに目立ったのはアジアの飲食系フランチャイズでした。タイでのこのようなBtoBイベントでは、試食の食べ歩きも楽しみであり、各ブースでは思い思いに食材を試食しながらわいわいと商談が進んでいます。
-
Sukishi Korean Charcoal Grill:家族層に好感の韓国式BBQ。韓流&韓国旅行体験が後押し。
-
Mikucha(タピオカティー):若年層ドリンクの定番。台湾旅行の体験需要が原動力。
-
COCO WALK(ココナッツドリンク):健康志向×タイらしさで着々と支持拡大。
-
ボートヌードル:仲間や家族で楽しめる「わんこ式」おかわりの楽しさで幅広く浸透。

実は、アジアの食がタイで広がっている背景には、ソースメーカーがタイ人の嗜好に合わせた多様な味のソースを提供するようになったことがあり、それが新商品開発のハードルを下げる要因にもなっています。
39 RAMEN特別講演(成長ストーリーと実務ノウハウ)
急成長中の日本式ラーメン39 RAMENは、特別セミナーで「小規模店舗から全国展開」の軌跡を公開。
-
ブランディング&マーケ:価格帯・体験価値・出店立地の一貫設計。
-
フランチャイズ運営:品質担保のスーパーバイザー導入、オペ標準化、仕入れ共同化、教育体系。
-
市場開拓:郊外モール→幹線道路沿い→地方中核都市へ段階展開した、とのこと。
最大の特徴は1杯39バーツ(約175円)という圧倒的低価格で、「手軽に食べられる日本食」市場を牽引。背景にはタイでの日本ラーメン人気の広がりがあり、石川県発祥の8番らーめんなどローカル展開が全国に浸透。さらに市場の価格帯は約39〜450バーツと厚みがあり、一風堂や神戸本店 Enishi(ミシュラン掲載)では400バーツ超(約1,800円〜)の高価格帯も成立しています。39 RAMENはこのタイ多層市場の“ラーメンエントリー層”を押さえた戦略で存在感を高めており、39バーツというインパクトはBtoB会場でも目立ったようです。

タイ進出時はC2C2Bを意識
タイ市場にはC2C2B(Consumer to Consumer to Business)が根づいています。旅行で体験した食文化が口コミで広がり、市場を形成し、ビジネスに発展する流れです。韓国式BBQ、タピオカ、日本ラーメンの浸透もこの「旅行体験の逆輸入」が土台です。
近年、タイ人の間で日本食が日常に溶け込むスピードは飛躍的に加速しており、それを裏付けるように訪日タイ人の数も力強く回復しています。2024年には114万8,900人に達し前年から15 %増、2025年上半期だけでも68万50 0人に達して前年比10 %増と、コロナ前の状況とは明らかに違う勢いです。
しかしながら、タイ市場は世界のトレンドを素早く取り込む一方、日本企業には訪日体験と現地消費を橋渡しする設計が欠かせません。
①まずはイベントやタイフェックスなどで試食提供し市場の反応を確認、
②信頼できる現地ディストリビューターと契約して小ロット検証、
③共同購買・共同物流によるコスト圧縮、
④ヒット後に現地生産やOEMへの段階的移行を検討——
この流れを通じて、関係者全員に利益が行き渡る持続的な生産・流通体制を築けるかどうかが勝負どころです。
当イベントのようなBtoB商談会は、成功事例と課題を同時に比較できる、海外展開を考える企業にとって貴重な学びの機会です。
業界別の最新状況や、今後のイベント・商談会についてもお気軽にお問い合わせください。
アジアクリック 高橋学
【出典】SMART SME EXPO 2025 主催者公式発表(2025年8月10日)
MGR ONLINE
2025年、中国はタイとの国交樹立50周年を記念し、複数の文化・観光関連イベントを実施。中国政府および地方自治体が主導し、タイとの関係強化と観光誘致を積極的に進めています。
タイ・中国国交樹立50周年記念イベント(バンコク)
2025年7月30日、バンコクの中国文化センターにて「中国・タイ国交樹立50周年文化交流イベント」が開催。
当日は、少林寺武術団による演舞や中国伝統料理の展示が行われた。タイ観光業界からも関係者が参加し、文化交流と観光協力の意義を再確認する機会となりました。


同センターはMRT(地下鉄)「Thailand Cultural Centre駅」近くのラチャダー通り沿いに位置し、これまでも中国文化普及の拠点として機能しています。
「サワディー&ニーハオ」プロジェクト🇹🇭🇨🇳
2025年5月29日~6月1日、バンコクのセントラルワールドにて「Sawasdee Ni Hao(サワディー・ニーハオ)」イベントが開催。
このイベントは中タイ国交50周年を祝う大型プロジェクトの一環であり、両国の観光・経済分野の連携強化を目的として実施されました。
タイ政府関係者の出席に加え、中国からも複数の観光局代表・重鎮が来泰し、現地メディアや旅行業界向けにプロモーションを展開しました。
 タイ首相経験者のペートーンターン氏も中国語でメッセージを伝えました
タイ首相経験者のペートーンターン氏も中国語でメッセージを伝えました

タイ元副首相のピニット氏「特に少林寺の伝統は、困難に直面しながらも自衛と生存を求めた実生活の闘いを描いた無数の映画にインスピレーションを与えてきました。」
エアアジアによる中タイの記念機体運航✈
2025年7月9日、タイ・エアアジアは国交樹立50周年を記念し、特別塗装を施した記念機(エアバスA320)を発表。
機体には、タイのナーガと中国の龍をモチーフとした記念ロゴが描かれ、観光誘致キャンペーンの象徴として運航が開始されました。

この取り組みは、両国の象徴を組み合わせたビジュアルを通じ、航空・観光分野の連携強化、ひいてはタイをはじめとした航空分野における“一帯一路”の拡張を、国内外、特に東南アジアにアピールする狙いがあります。
中国の各地方がタイ人誘致を強化、一帯一路の地ならしの側面も
中国の地方自治体も積極的に・個別にタイ人観光客の誘致を進めています。特に雲南省、広東省、海南省などでは、タイ語に対応した観光資料の作成やオンラインキャンペーンを展開しており、中国南部の自治体や航空会社を中心にファムトリップも積極的に実施しています。
また、ご存じのとおり、タイにおける中国ツアーの参加費用は、訪日ツアーの数分の一となっています。
ご参考までに、中国ツアーのスクリーンショットを以下に掲載しています。
(タイ最大手の旅行会社であるQuality Expressによる中国ツアー)

(2025年8月、タイ有力旅行会社Compax world – ASAHI travelによる「プレミアム中国ツアー」シリーズ広告。例年に比べて中国ツアーがよく売れるとのこと)

観光インバウンドは中国にとって「収益事業や地方活性化」にとどまらず、「外交・覇権戦略の一環」として位置づけられており、特に東南アジアにおいては「一帯一路」と密接に結びついています。したがって、日本が東南アジアからの訪日誘致を進める際には、現場レベルでも知らず知らずのうちに中国の影響圏(投資・交通インフラ・人材交流)と競合していることを強く意識する必要があります。
アジアクリック 高橋学
参考URL
-
タイ外務省(MFA)公式発表(50周年レセプション報告)
https://www.mfa.go.th/en/content/golden-jubilee-of-thailand-china-friendship-en -
エアアジア記念機体ラッピング(THAICH.NET)
https://www.thaich.net/news/20250710ew.htm -
Sawasdee Ni Hao イベント(NEWSCLIP)
https://newsclip.be/thai-news/thai-economy/23023 -
少林寺武術団による記念公演(Bangkok Post)
https://www.bangkokpost.com/thailand/pr/3078890/shaolin-performance-marks-50-years-of-thai-sino-ties - Comapax world facebook
https://www.facebook.com/compaxworld
2025年7月25日から8月3日まで、タイ・バンコクにある商業施設「ザ・モール ライフストア バンカピ(M GRAND HALL, G階)」にて、定期定期に開催されているプロモーションイベント「THE MALL JAPAN DISCOVERY 2025」が仙台の七夕祭りをテーマとして開催されました。

本イベントでは、宮城県仙台市が観光と食の両面でタイ市場に向けたプロモーションを実施。既存の「SUGOI JAPAN」イベントの仙台バージョンとして、東北ならではの魅力を発信しました。
会場演出・体験コンテンツ
会場は仙台七夕まつりをイメージした華やかな吹き流しで彩られ、日本らしい雰囲気が漂っていました。
タイ人来場者は、短冊に願い事を書く体験にも参加し、「家族の健康」や「幸せ」など、思い思いのメッセージを日本文化に倣って記していました。
さらに、浴衣を着て日本式の人力車(じんりきしゃ)に乗る体験も提供され、家族連れを中心に人気を集めていました。
また、仙台市の公式観光キャラクター「むすび丸」も登場し、記念撮影などを通して交流を深める姿が多く見られました。


ステージ上では「DAISUKE SENDAI – LEGEND OF SAMURAI」と題した本格的な時代劇パフォーマンスが行われ、映画のような演出に会場全体が引き込まれていました。子どもから大人まで、タイ人参加者から非常に高い評価を得ていたのが印象的です。

仙台・宮城の特産品販売
物販コーナーでは、仙台や宮城県の特産品が多数紹介・販売されていました。中でも注目されたのは以下のような商品です。
-
仙台牛の焼き実演
-
ずんだ餅やずんだスイーツ
-
喜久福(抹茶大福)
-
いかめんたい、もずく、そうめんなどの海産加工品
グルメを通じて、仙台の食文化に触れられる機会として、試食や購入を楽しむタイ人来場者の姿が多く見られました。

バンコクの中間層は日常的に日本料理を食べるようになってきており、一通りの日本料理は揃っているため、昨今は特に地方料理に興味が向けられています。
タイ市場へ進出する意義
現在のタイ市場では、訪日旅行先の選定基準として「地方らしさ」や「食体験」が強く求められています。中間層・富裕層ともに旅行意欲は高く、タイ語でも地方へ訪問するための情報はそろっていますので、たくさんある候補地の中でもSNSを通じた情報拡散や刷り込みによって「まだ知られていない魅力的な地方都市や地方」を訪問先として選ぶ傾向がますます強まっています。
また先にも触れたとおりバンコクの訪日リピーターにとって、本物の食、まだ食べたことのない地方ならではのグルメは訪問地候補に入るためのでも重要な要素の一つであります。
仙台市のような地方中枢都市は、東京・大阪とは異なる独自性あるコンテンツを「東北・東日本としての広域周遊で」提供できるため、今後の訪日インバウンドにおいて、タイ人訪日リピーターにとってとても有望なディスティネーションであり、その意味で、今回のように現地イベントを通じて体験的に訴求する手法は、非常に効果的なPRアプローチと評価できます。
その他、昨今のタイや東南アジアでの有効な最新プロモーション事例などはお気軽にお問い合わせください。
アジアクリック 高橋学
2025年7月24日から27日にかけて、バンコクのBITECで開催された「Pub Bar Asia 2025」が、パブ・バー・ナイトライフ業界向けに、5,500名以上もの世界中のサプライヤーがタイおよびASEAN市場向けの商品やサービスを紹介し、今年も大きな注目を集めました。


昨今のタイでは、過去10年間で平均5〜7%のアルコール市場の成長が見られ、有名なタイビールやタイウイスキーに加え、近年ではクラフトジンやフルーツリキュールなどの新興カテゴリーも、一般消費者の間で急速に浸透しています。
また、中間層の拡大とタイ観光業の回復を背景に、差別化されたプレミアムアルコール製品への需要が高まりつつあることも注目すべき市場動向です。
その中でも特に多くの来場者の関心を集めていたのが、日本パビリオンに展開された日本酒のブース群です。


今回は全国から15の酒蔵・関連団体が参加し、それぞれ自慢の日本酒を携えてタイ市場にアピールしていました。横田酒造(埼玉県)、小林酒造(北海道)、小西酒造(兵庫県)、松井酒造(京都府)、菊水酒造(新潟県)、関空運輸(大阪府)といった伝統ある酒蔵や輸出支援業者が出展されており、それぞれの地域色を活かした日本酒を紹介していました。
そのほかにも、宮崎県からは宮崎本店(宮崎県)が、京都府からはLIKAMAN HOLDINGS(京都府)が、静岡県からは三源(MITSUGEN CO., LTD.)(静岡県)が出展。果実系リキュールやクラフト系蒸留酒など、幅広いジャンルでの出展が見られました。
これらの企業は、タイの飲食・流通業者との商談に加え、現地消費者の嗜好に合わせたプレゼンテーションを行っており、日本酒の多様性と可能性を強く印象づける展示となっており、各ブースでは試飲や商談が熱心に行われ、バイヤーや業界関係者、一般のお酒好きまで、幅広い層が足を止めていました。
タイにおける日本酒市場は、この10年で大きく成長しています。日本酒の対タイ輸出額は過去10年で約2倍以上に拡大し、特にプレミアムな純米大吟醸や吟醸酒の需要が目立っています。輸出単価も2013年には1リットルあたり約650円だったものが、2023年には1,400円を超えるまでに上昇しました。これにより、日本酒はかつての「和食のお供として雰囲気・セルフィー用に呑む」から、「こだわりとストーリーのある高級酒」、「自分の大切な時間に呑む高級酒」へと位置づけが変わりつつあります。

市場の嗜好にも変化が見られます。バンコクでは高級レストランや寿司店に加え、近年はホテルラウンジやワインバーなどでも日本酒が提供されるようになっており、料理とのペアリングやカクテル素材としての活用も進んでいます。一方で、純米酒やスパークリング系の日本酒は、若年層や女性層を中心に、カジュアルな飲み方として親しまれ始めています。
Pub Bar Asia 2025への参加を通じて、日本酒は「飲んでもらう」フェーズから「選んでもらう」「語ってもらう」フェーズへと進化しつつあることが感じられました。今後もタイ市場は、日本酒にとって重要な海外市場の一つであり続けるでしょう。地元に根ざした小規模酒蔵にとっても、現地とのつながりを深めながら長期的に取り組めるチャンスが広がっています。
そして、すでに日本酒文化が深く根付き、高品質な銘柄の輸入・流通が当たり前になっているシンガポールのような成熟市場を参考に、タイ市場も今後さらに洗練された日本酒の受け入れが進むと期待されています。日本酒が「特別な体験」として日常の中に浸透していく未来は、もう遠くないかもしれません。
個人的に印象に残ったのは、スマートフォンのアプリを使って運転代行業者を呼べるサービス「わたし呑む・あなた運転する」の展示でした。

今後も、8月の29日から31日の期間にバンコク都心のイベント会場クイーンシリキッド・ナショナルコンベンションセンターで日本博2025が、高級百貨店エムスフィアでSAKE WEEK THAILAND 2025が開催されます。 この機会にコロナ禍前とは大きく変化したタイ消費者市場を視察されるのも効率的かと思います。
タイやシンガポールへの輸出、プロモーションについては、お気軽にご相談ください。
アジアクリック 高橋学






マガンダンハポン! フィリピン特派員のオムです。
フィリピンには、ミリエンダという習慣があります。
ミリエンダとは「おやつ(Snaks)」のこと。なんと1日2回も、食事とは別に間食をする習慣があるんです!
7時 朝食
10時 ミリエンダ
12時 昼食
15時 ミリエンダ
18時 夕食
おおよそフィリピン人の約半数がミリエンダ(間食)をしている様子で、特に何を食べるかは個人により異なりますが、インスタントヌードルやサンドイッチなどパンとコーヒーを家族や友人などその場に居合わせた人々とおしゃべりやテレビを見ながら食べます。
JETROの2012年の調査「アジア主要国のビジネス環境比較」でも日系企業のフィリピン進出業種の約3割が飲食業となっておりこれはアジア一です。外食でミリエンダを食べる人も多く、メトロマニラの中間層であれば1回に一人単価 600〜800円ほどかけることも珍しくはありません。
飲食店にとって見れば、フィリピンには1日5回顧客が購入するチャンスがあることになりますね。
人口1億を超え、ますます中間層に厚みが出るフィリピン。
飲食業でまだの方は、マニラにぜひ視察に来てみてはいかがでしょうか?
(マニラ特派員/オム)
 日本語
日本語 English
English
